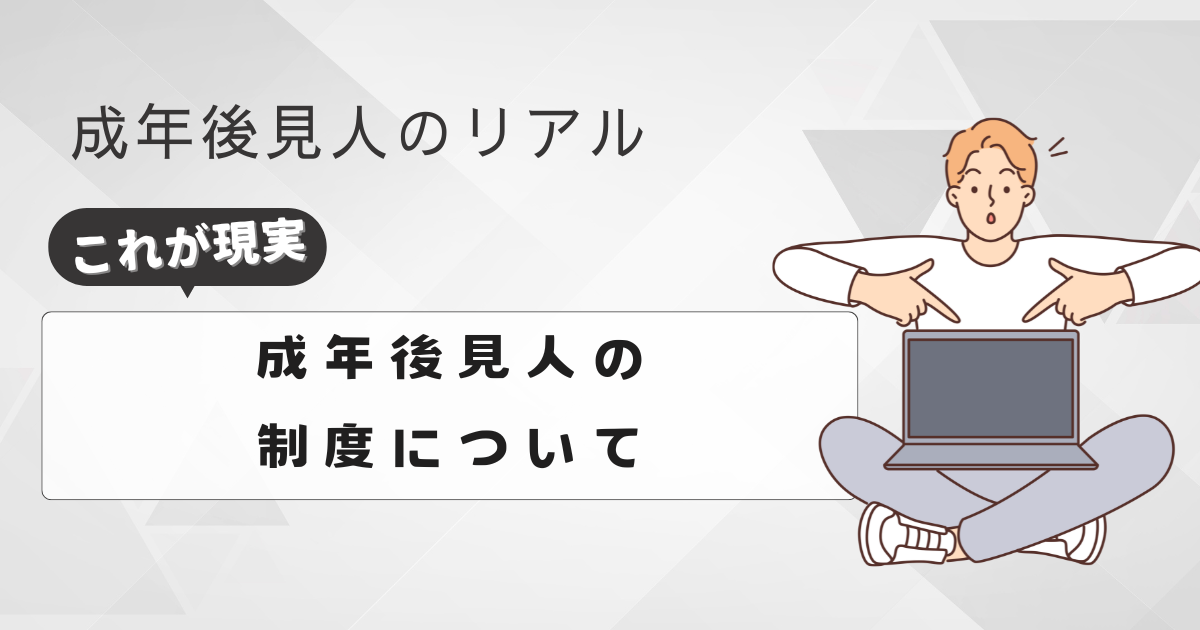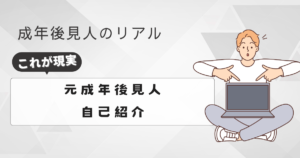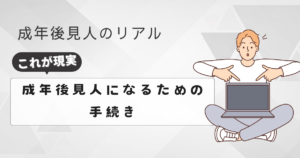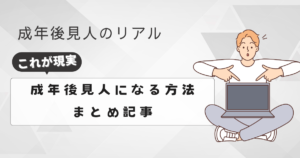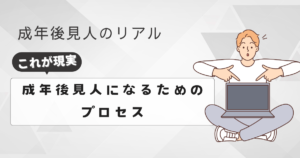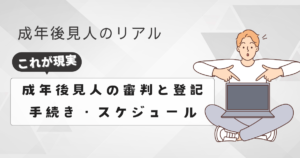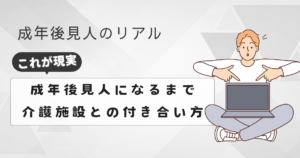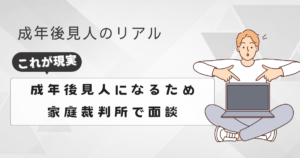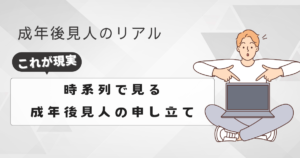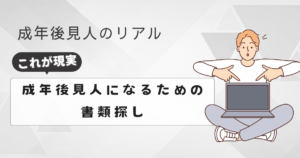目次
はじめに
こんにちは、くじら99(@9jira99)です。
現在50歳、会社勤めをしながら、地方に暮らす親族の成年後見人を3年間務めました。
「成年後見人って、何をするの?」「どうやって選ばれるの?」
そんな疑問を持っている方へ、私の体験を通して、制度の実際をお伝えします。
成年後見人制度とは?|認知症・障害などによる“法的支援”の仕組み

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方を法律的に支援する制度です。
家庭裁判所の監督下で、選ばれた「後見人」が生活や財産管理を代行します。
✅ 成年後見人の主な役割
- 財産管理:銀行口座・不動産・各種契約の管理や支払い
- 生活支援:介護・医療施設との連携、生活費の用意
- 法的代理:契約締結や解約など、本人に代わる意思決定
✅ 種類ごとの違い
| 制度 | 対象者の状態 | 主な支援内容 |
|---|---|---|
| 後見 | 判断能力がない | 全面的に代理 |
| 保佐 | 著しく不十分 | 重要な契約などを代理・同意 |
| 補助 | 一部不十分 | 特定業務のみに限定してサポート |
私が成年後見人を引き受けた理由|遠方・知識ゼロからのスタート
きっかけは、叔父(Aさん)が倒れたという突然の連絡でした。
親族の多くが高齢で対応できず、比較的若く動ける私が白羽の矢を立てられたのです。
とはいえ、300km以上離れて暮らす私にとって、制度の理解も実務の手続きも、すべてが未知の世界でした。
成年後見の申立て手続き|弁護士に依頼した理由と実際の流れ
🔹申立てに必要な手続き
- 初回相談(弁護士事務所や市区町村の窓口)
- 必要書類の準備(申立書、診断書、財産状況資料など)
- 家庭裁判所への提出と審査
- 後見人選定と登記
🔹費用の内訳(目安)
- 申立手数料:約3,400円
- 郵便切手代:2,000~3,000円
- 診断書作成費:5,000~10,000円
- 戸籍・住民票取得費用:数百円
🔹弁護士を頼った理由
私は仕事をしながらの対応で、書類作成や裁判所とのやり取りに時間を割く余裕がありませんでした。
そのため、制度に詳しい弁護士に依頼。申立ての正確性や迅速さ、精神的な安心感が得られました。
💡申立て費用は原則として申立人の負担となります。ご注意ください。
成年後見制度の限界と代替手段|任意後見・信託という選択肢
後見制度は有効な一方で、「柔軟性が乏しい」「家庭裁判所の監督が厳しい」という制約もあります。
そのため、次のような制度も併せて知っておくことが大切です。
🟢 任意後見制度
- 判断能力があるうちに、将来の後見人を契約で指定しておける制度。
🟢 家族信託(民事信託)
- 家族に財産の管理・処分を信託する制度。
- 後見制度よりも自由度が高く、相続・認知症対策にも活用できます。

まとめ|“制度を知る”ことが、家族を守る第一歩

成年後見制度は、判断能力が低下した方の「生活」と「財産」を守るための制度です。
ですが、手続きの煩雑さや費用の負担、自由度の制約を考えると、必ずしも万人向けではありません。
私は弁護士に相談しながら申立てを進めましたが、時間も体力も使う大きな経験でした。
もし、あなたのご家族が将来認知症になるかもしれないという不安があるなら、
今からできる準備=「任意後見」「家族信託」をぜひ知っておいてください。
次回予告
次回は、「実際に成年後見人としてどんな業務を行ったか(施設手続き・財産管理など)」を具体的にご紹介します。