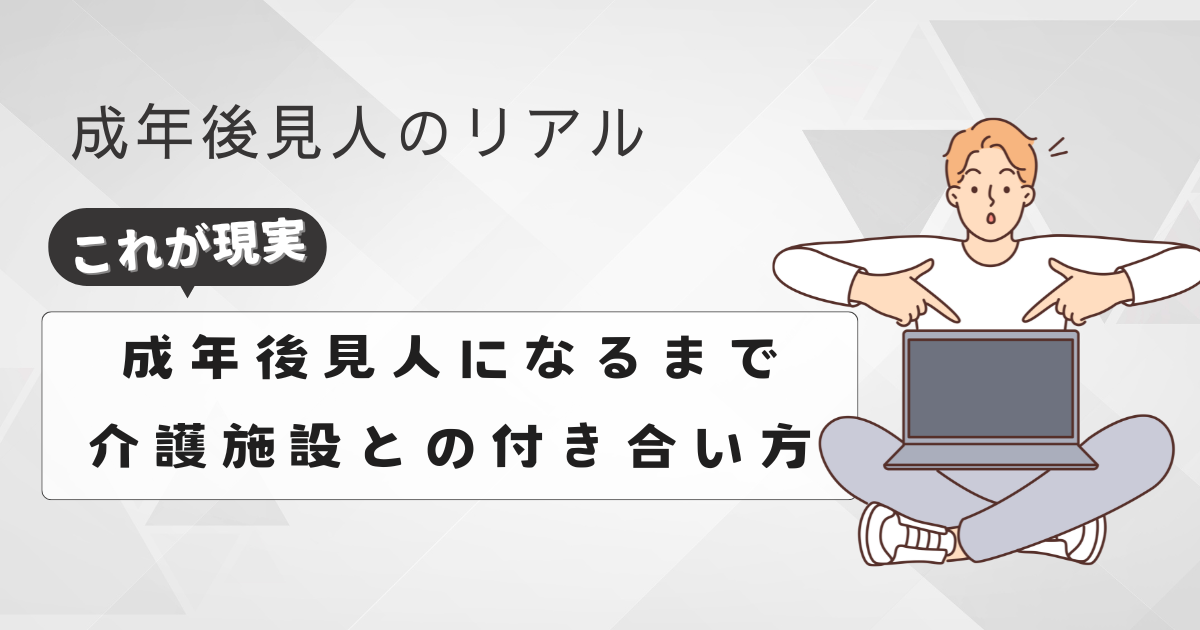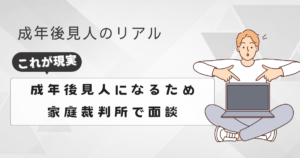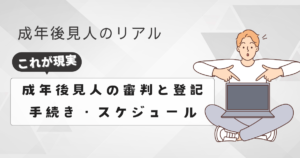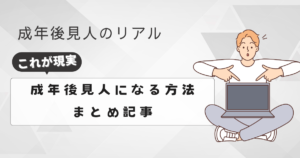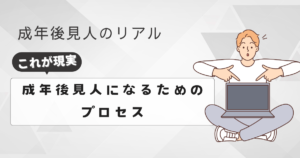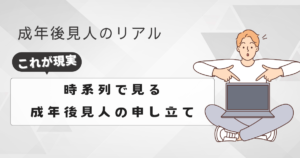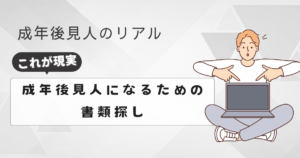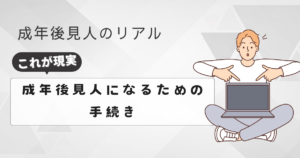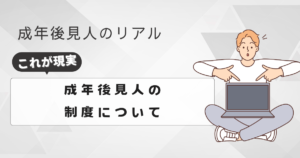目次
はじめに
成年後見人経験者のくじら99(@9jira99)です。
この記事では、成年後見人として介護施設とどのように連携したか、そして施設選定や認知症対応についてリアルな経験を基に解説します。
親の介護や認知症リスクが気になる方にとっても役立つ内容になっています。
成年後見人と介護施設の関係

成年後見人になると、最も多く連絡を取るのが「介護施設の担当者」です。
ご本人Aさんは措置入院後、ショートステイを経て、有料老人ホーム、特別養護老人ホームへと入所していきました。
このプロセスの中で、以下の点が重要になります:
- ご本人の状態に応じた施設の選定
- 担当者とのこまめな連絡
- 手続き進行状況の共有
- 支払いの猶予依頼
親切な担当者に恵まれたことが、非常に大きな助けとなりました。
ショートステイから始まる施設選び

措置入院後の受け皿
Aさんは退院後、最初に「ショートステイ」に入所しました。
ここは一時的な施設であり、早急に次のステップを考える必要がありました。
施設の段階的移行
- ショートステイ:緊急入所・短期滞在
- 有料老人ホーム:特養の空き待ち期間を埋める
- 特別養護老人ホーム:最終的な長期入所先
施設ごとの費用も異なり、特養を最終目標として進める必要がありました。
介護施設担当者との信頼関係がカギ
Aさんの担当相談員は非常に親身に対応してくれました。
関係構築で大切にしたこと:
- こまめな連絡:裁判所面談や審判の進捗を共有
- 支払い猶予のお願い:登記前の費用対応を調整
- アドバイスの傾聴:施設選び、支援方針などで助言を得る
- 現地訪問時の顔出し:距離があっても直接の対話を重視
施設側としても、後見人がどういう立場でどう動いているのかが見えると、支援しやすくなります。
Aさんの認知症と介護対応

Aさんはアルツハイマー型認知症を患っていました。
担当者からのアドバイス:
- 行動変化への理解と柔軟対応
- 面会時の対応方針(意思疎通困難)
- 安全確保の体制づくり
- 家族や後見人との連携強化
認知症の進行に応じて施設の選択や支援の内容が変わっていくため、常に情報交換が重要です。
成年後見人としての具体的業務
- ショートステイ施設担当者との連絡・面談
- 有料老人ホームの選定と入所準備
- 成年後見人の申立~審判手続きの報告
- 支払い猶予のお願い
- Aさんの体調変化のモニタリング
契約や金銭の手続きは後見人にならないと進められないため、準備だけ先に整える必要があります。
家族信託という選択肢も
もし、まだ認知症になっていない親がいるなら、家族信託の活用を強くおすすめします。
家族信託のメリット:
- 認知症による資産凍結を防げる
- 財産の管理・運用・処分を家族に任せられる
- 後見制度よりも柔軟で、費用も比較的安価
▼ 詳細はこちらの記事をご覧ください:

まとめ
介護施設の担当者との連携は、成年後見人業務のなかでも要となる部分です。
こまめな連絡、信頼関係の構築、柔軟な対応が被後見人の安心・安全な生活を支えます。
今後、親が認知症になるかもしれない、または遠方で心配だという方は、早めに備えることが重要です。
その一つの手段が「家族信託」です。親が元気なうちにこそ、話しておきたい制度です。
次回は、審判が始まり成年後見人として正式に活動を始める話をお届けします。
認知症による資産凍結を防ぐために
家族信託という新しい備え
ご存知ですか?
親が認知症になると、預金の引き出しや自宅の売却などができなくなり、まさに「資産が凍結」されてしまいます。
将来の介護や医療のために備えていた財産が、使えなくなるリスクがあるのです。
そんな事態を防ぐ手段として、近年注目されているのが「家族信託」です。
家族信託は、親が元気なうちに家族に財産管理を託すことで、認知症による凍結を回避できる法的な仕組みです。
家族信託の専門家に相談できる無料サービスなら、家族信託の「おやとこ」。
年間数千件の相談実績があり、全国7拠点で対応しています。
ご興味のある方は、下記のURLリンクまで。
※外部サイト「家族信託のおやとこ」に移動します