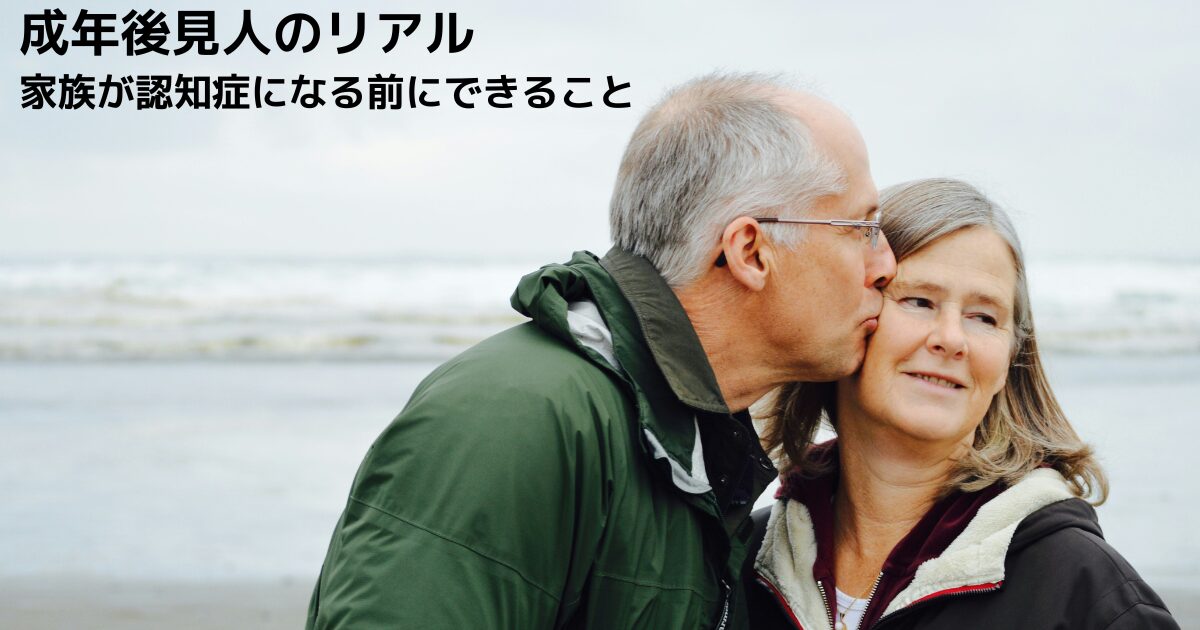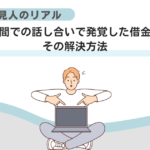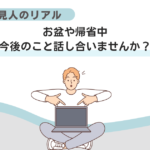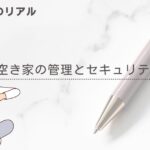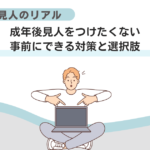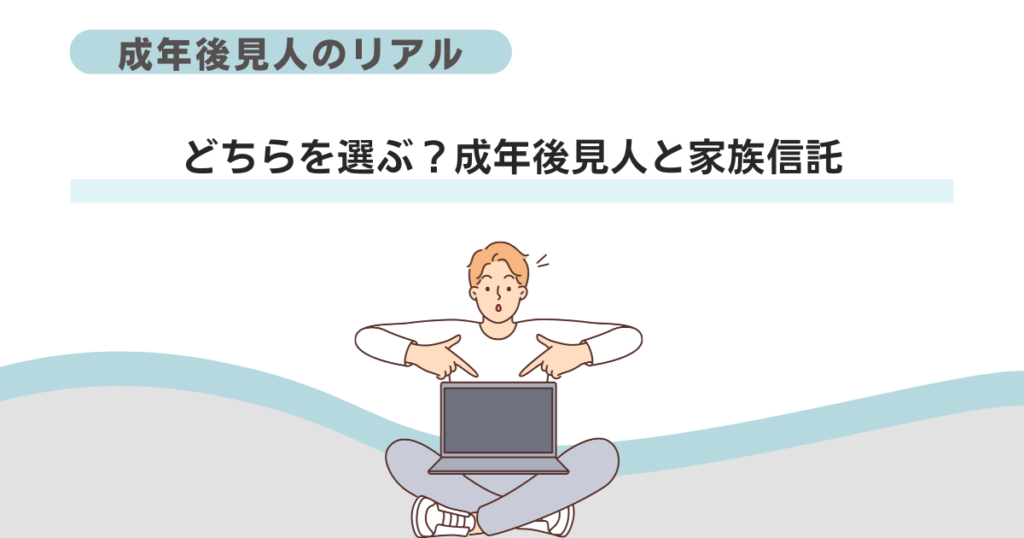認知症による資産凍結に備える|成年後見・家族信託・相続の手続きブログ

成年後見人のリアル
※本サイトは、プロモーションを含みます。
このブログについて
「realkouken.com」は、成年後見制度や家族信託、相続手続きに悩むすべての方へ向けた、実体験に基づく情報ブログです。
成年後見人としての経験をもとに、法制度との向き合い方、手続きの現実、必要な備えを記録・共有するものです。
同じように誰かを支えようとしている方の一助になればと思います。
親の認知症、財産管理、遺産の分割…。
法律の専門家ではない“一般の人”として、私が学んだことを丁寧にお伝えします。
今や高齢者の5人に1人が認知症と言われています。
私は、とある理由で認知症になった親戚のため、成年後見人という仕事をしました。
このブログでは、成年後見人になって実際に経験したことを共有します。
この成年後見人という仕事はご本人の生活・財産を守るため大切な仕事です。
成年後見制度の基本と手続き
認知症の親や親戚を支えるための法的手段。申立てから報告義務までを実務的に解説します。
詳しくは、下記のバナーをご確認ください。
私が経験した、具体的な成年後見人の記録は下記のカテゴリーからご確認ください。
家族信託の仕組みと活用法
将来の不安に備える柔軟な仕組み。
後見との違いや活用場面を具体的に紹介します。
家族信託の仕組みと活用法|“まだ間に合う”備えの選択肢
家族信託とは、認知症などで判断能力が低下する前に、信頼できる家族に財産の管理・運用・処分を託す制度です。
成年後見制度と異なり、家庭裁判所の監督を受けずに柔軟な設計が可能であり、財産の凍結を防ぐ手段として注目されています。
家族信託を検討する際の参考として、以下のポイントを押さえておくと良いでしょう:
- 信託契約書の作成:家族信託を行うには、信託契約書を作成する必要があります。契約内容には、信託の目的、信託財産、受託者の権限などを明確に記載します。
- 信託口口座の開設:信託財産の管理には、専用の信託口座を開設することが望ましいです。これにより、財産の管理が明確になり、トラブルを防ぐことができます。
- 信託登記の手続き:不動産を信託財産とする場合、信託登記を行う必要があります。これにより、信託の効力が第三者に対しても及ぶようになります。
家族信託は、将来の不安に備えるための有効な手段ですが、契約内容や手続きには注意が必要です。
実務上は、専門家・家族信託を扱う会社のサポートが必要です。
認知症による資産凍結、その前にできること
親がもしも認知症を発症したら――
通帳からお金が引き出せない。
自宅を売って施設費用に充てようにも、名義人の判断能力が失われていて売却できない。
そんな“資産凍結”のリスクが、現実のものとして多くの家庭を悩ませています。
💡 でも、実は事前に「家族信託」という仕組みで備えることができるのをご存知ですか?
家族信託とは、親が元気なうちに財産の管理・運用を家族に託す制度。
将来、認知症によって判断能力が低下しても、家族がスムーズに財産を管理・活用できるようになります。
✅ 専門家に無料で相談するなら「家族信託の おやとこ」
「家族信託って難しそう…」「うちの場合はできるの?」
そんな疑問を解決してくれるのが、全国7拠点・年間数千件の相談実績を持つ**家族信託の専門サービス『おやとこ』**です。
\ まずは無料で相談してみませんか? /
詳細は、下記の記事をご覧ください。

相続手続きと準備の実務
遺産分割・銀行対応・不用品処分まで。現場視点で実務の流れを整理しています。
相続手続きと準備の実務
相続は「誰が何を相続するか」だけでなく、銀行・保険・証券の名義変更、遺品の整理・不用品の処分など、多くの実務が伴います。
現場視点での相続の進め方について、具体的にご存知の方は少ないのではないでしょうか?
相続の手続き、全部やるのは大変だと感じたら
相続は、戸籍収集・金融機関対応・遺産分割協議・不動産登記など、やるべきことが多岐にわたります。
相続の手続きは、思っている以上に「やること」が多く、ひとつひとつが煩雑です。
たとえば、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を全て集めるだけでも、
本籍が転々としていれば、複数の自治体に郵送請求しなければなりません。
金融機関では、残高証明・口座凍結解除・解約のために、
相続人全員の署名・押印が求められ、遺産分割協議書も作成しなければ進みません。
不動産があれば、相続登記の申請も必要で、
法務局へ行くか、司法書士に依頼するなどの対応が必要です。
しかも、こうした作業は期限に追われるものも多く、
通常の仕事や生活と並行して行うには、心身ともに大きな負担になります。
「何から始めればいいかわからない」「書類が多すぎて混乱する」「親族間で意見が合わない」――
そんなとき、信頼できる代行サービスに任せるという選択肢もあります。
相続手続き、まるごと安心して任せたい
相続の実務に疲れたとき、頼れる選択肢がここにあります。
慣れない作業に疲れたとき、信頼できる代行サービスに任せるのもひとつの選択肢です
相続手続き代行サービス「nocos(ノコス)」をご存知ですか?
※外部サイト「nocos(ノコス)」に移動します